【千葉県佐倉市】猫 及び 猫の飼育に関する事
ペットを飼うときには
フン尿の始末をしましょう
- 飼い犬は家でトイレを済ませるようにしつけましょう。
- 散歩中はできるだけペット用のおむつ等を活用しましょう。
- 散歩中にしてしまったフンは、必ず持ち帰ってください。また、おしっこをしてしまった場合は、携帯したペットボトルの水をかける等の処理をしましょう。
- 他人の家の門柱や車等にさせないようにしましょう。
放し飼いは禁止です
- 犬は鎖等でつなぐか、柵等の中で飼わなければなりません。
- 散歩には制御できる長さのリードをつけましょう。
- 猫も室内で飼いましょう。家の外は交通事故や病気の感染の危険があるほか、他人の家でフンやおしっこをして迷惑をかける可能性があります。
- 野良猫などの野生動物へ餌やりをするのもやめましょう。
しつけをしましょう
- 犬の無駄吠えなどの行動がご近所トラブルの原因になります。しつけをすることで人間の社会生活に適応させ、飼い主との関係を正しく確立させることができます。
- 飼い主も動物の本能や習性を学んで問題行動の軽減に努めましょう。
健康を管理しましょう
- ワクチン接種、ノミやダニ、フィラリア等の寄生虫の駆虫など、獣医師の診断のもとに、動物を適正に管理しましょう。また、動物の体調に異変があった場合は、速やかに獣医師に診せましょう。
- 動物から人に感染する病気について正しい知識を持ち、人への感染防止に努めましょう。
最期まで責任を持ちましょう
飼い主はその動物が最期を迎えるまで飼う責任があります。
- 動物を飼うときは、その動物の習性、行動、特徴等を把握するとともに、飼うにあたってはどれくらい成長するのか、費用もどれくらい要するかを事前に調査しましょう。
- どうしても飼えなくなってしまった場合は、飼い主又はご家族などが、親族や知人、ご近所の方など、直接引き取り先を探してください。
迷子にさせない
- できるだけ屋内で飼育し、脱走しないように注意しましょう。
- 連絡先を記載した札(迷子札)を首輪に付け、犬や猫の場合はマイクロチップを装着・登録し、迷子になっても保護された際に飼い主に連絡がとれるようにしておきましょう。
- 犬の場合は「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を装着させましょう。
- 迷子になってしまった場合は、保護の情報が入っている可能性がありますので、市生活環境課(電話043-484-6148)・県動物愛護センター(電話0476-93-5711)・佐倉警察署(電話043-484-0110)にお問い合わせください。
- 県動物愛護センターのホームページでは、収容動物や保護動物の情報が閲覧できます。
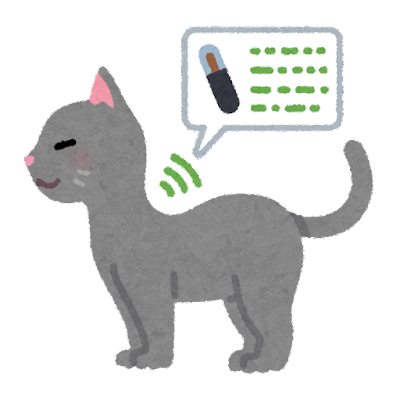
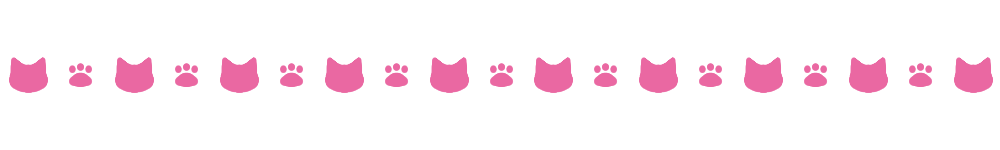
ペットの災害対策について
災害時に大切なペットと避難をするためには、日ごろからの準備が必要になります。以下のことを確認し、災害時の対策を講じておきましょう。
- (注意)本市の避難所では同行避難が認められておりますが、人の居住スペースとは隔離された所定の係留場所で、飼い主自身が管理することが原則となります。
- (注意)危険動物の同行避難は受け入れられません。
日ごろの準備
- しつけ
無駄吠えをさせない、ケージにおとなしく入らせる、トイレを決められた場所でさせるなど - 健康管理
狂犬病予防注射、その他ワクチンの接種など - 犬鑑札や迷子札での身元(所有者)表示
犬が迷子になって保護された際に所有者を特定することができる - ペット用防災用品
食料、水、ケージ(雨風に強いもの)、リード、トイレ用品 - 避難所やペットホテル
避難所への経路の把握、台風など予期できる災害時にペットホテルを利用
避難所での対策
- ケージを利用
風水害に備え雨風に強いケージを利用し、毛布などで防寒対策をする - リードを利用
ケージがない場合はリードで係留する - 管理
定期的にペットの状態を確認し、排泄物の処理や健康管理をする

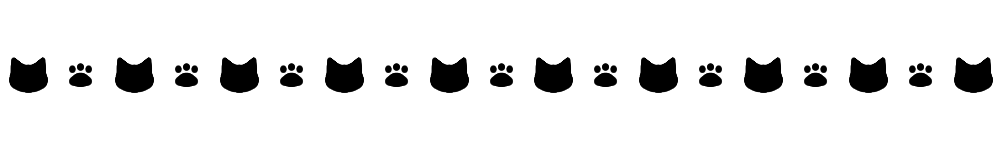
ペットを海外へ連れていく方へ
動物の輸入届出制度について
平成17年9月1日から動物の輸入届出制度が導入されました。
この日以後には、海外からハムスター、リスなどの齧歯類、フェレットなどのほ乳類、インコなどの鳥類を国内に持ち込むこと(持ち帰ること)が非常に難しくなりました。ペットも対象ですのでご注意ください。詳しくは、厚生労働省検疫所のホームページをご覧ください。
犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽は、動物検疫所で輸入検疫が行われる動物であるため本制度は適用されません。これらの動物の輸入検疫制度に関しては、農林水産省動物検疫所のホームページをご覧ください。
平成15年に話題となったSARS(重症急性呼吸器症候群)をはじめ、世界では従来知られていないたくさんの感染症が次々に見つかっています。
日本は動物由来感染症が比較的少ないと言われています。その理由としては、日本が全体としては温帯に位置する島国であったこと、獣医学領域が中心となって家畜衛生対策、狂犬病対策を徹底して行ってきたこと等があげられます。
しかしながら、交通手段の発達による人とモノの大量移動、開発やそれにともなう自然環境の変化、動物性食品の生産体制の変化等が背景となって、今まで知られていなかった感染症が明らかになったり、忘れられつつあった感染症がその勢いを取り戻しています。今後は、動物の飼い主の自覚がより一層必要です。


[経済環境部]生活環境課(生活環境班)
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504
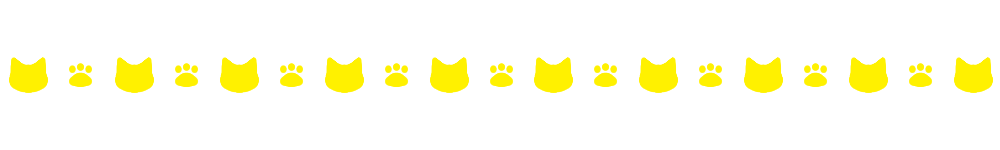
( 佐倉市役所公式ホームページより引用 )

