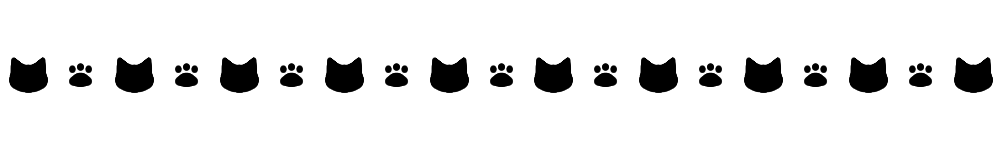【栃木県鹿沼市】猫 及び 猫の飼育に関する事
正しい猫の飼い方について
猫を飼うなら4S(エス)
S1 飼養頭数のコントロール(不妊・去勢)
猫は繁殖力が強く、1頭のメスから1年間に20頭以上の子猫が産まれることもあります。十分な手間とお金をかけてもらえない不幸な命を増やさないために、不妊去勢手術を行いましょう。
早めに手術を行うことでリスクを減らすことができる病気もあります。
鹿沼市では、メスの飼い犬および飼い猫を対象に不妊手術費の助成を行っています。
S2 終生飼養
猫の生態や習性を正しく理解し、飼い主の責任として、最後まで愛情を持って飼いましょう。
S3 所有者明示
室内で飼っていても、雷や花火などの大きな音に驚いてパニックになったり、窓やドアのわずかな隙間から出て行ってしまったりして行方不明になるケースがあります。首輪に迷子札(飼い主の名前、住所、電話番号を記載)をつけて所有明示をしましょう。
マイクロチップの装着は、外れる可能性がほとんどないため、より効果的です。
猫が迷子になった場合は、栃木県動物愛護指導センター、お住いの市町村の警察署、市役所(鹿沼市であれば環境課環境保全係)に連絡しましょう。
S4 室内飼養
猫は十分な食べ物があれば必ずしも広い空間を必要とせず、安全でストレスを発散できる環境を整えることによって、室内のみで飼養することができます。
交通事故や感染症の危険性、迷子、鳴き声や糞尿による近隣トラブルの回避につながることから、猫は室内で飼いましょう。
その他
野良猫に対して、かわいい・かわいそうというだけの無責任なエサやりは周辺の迷惑となるだけでなく、飼い主のいない猫をむやみに増やすことにつながります。無責任なエサやりはやめましょう。
※猫の正しい飼い方について詳しく知りたい方は、栃木県動物愛護指導センターHPに掲載されている「栃木県猫の適正飼養ガイドライン」をご覧ください。
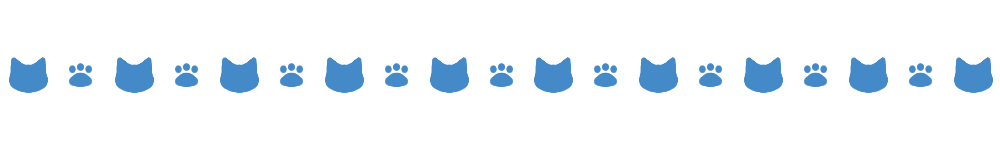
犬・猫のマイクロチップ装着義務について
犬猫販売業者等のマイクロチップの装着義務化について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります
指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
犬や猫の飼い主様へ
令和4年6月1日より前から飼育されている犬・猫へのマイクロチップの装着は義務ではありません。
しかし、マイクロチップを装着することで、犬や猫が迷子になった際や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった際に、飼い主の元へ帰れる可能性が高まるといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に指定登録機関への情報の登録を行う必要があります。

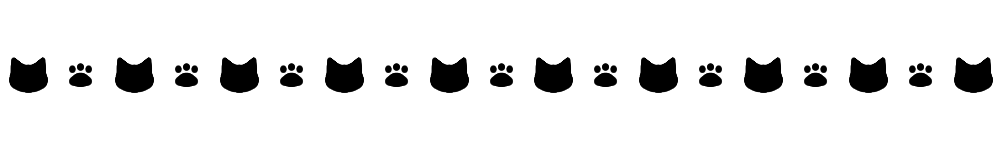
ペットの防災対策
人とペットの防災対策
災害時に、慌てずペットと避難できるように、防災対策について確認しておきましょう。
※避難所の状況により、ペットの受け入れができない場合もあります。
身の回りの防災対策
災害からペットを守るためには、日頃からの備えが大切です。
住まいの耐震強度の確認や補強、家具の固定など、対策を行いましょう。
また、首輪や鎖が外れたり切れたりして逃げ出す恐れがないか確認しておきましょう。
ペットのしつけと健康管理
人とペットがすみやかに避難できるように、普段からキャリーバックなどに入ることを嫌がらないようにしておきましょう。社会化やしつけは、他の人への迷惑となる行動を防止するとともに、ペット自身のストレス軽減につながります。
避難所等では、他の動物との接触が多くなるため、普段からワクチン接種など感染症予防をして、ペットの健康を確保しましょう。
所有者明示
災害発生時には、ペットと離れ離れになってしまう場合もあります。
保護されたときに飼い主さんのもとに戻れるように、迷子札などをつけておきましょう。
マイクロチップも有効です。
(※犬の場合は狂犬病予防法に基づき、鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着する義務があります。)
避難用品や備蓄品の確保
避難先でのペットの飼養に必要なものは、基本的に飼い主さんが用意しておきましょう。
(首輪、リード、ケージやキャリーバック、ペットフードや水、トイレ用品など)
また、備蓄品には優先順位をつけ、優先度の高いものは避難時にすぐ持ち出せるようにしておきましょう。